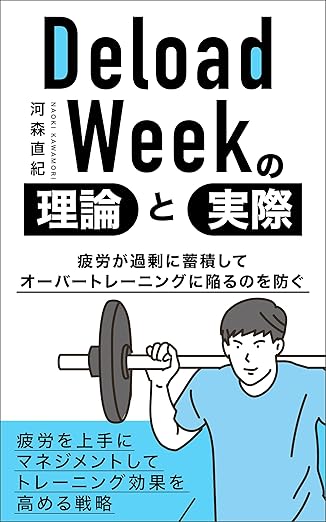
前提知識
まず、この書籍はfitness-疲労理論を前提に書かれているものなのでざっくりそれについてまとめます。
フィットネス-疲労理論
トレーニング刺激という入力を身体に与えたときに、どのような出力がどのくらい出てくるのか、そしてその出力が時間経過とともにどのように変化していくのか、を説明するものです。
「フィットネス(プラスの適応)」と「疲労(マイナスの適応)」の2つの要素の関係性に基づいています。この2つの要素が相互に作用し、その時々の身体のコンディション、すなわち「preparedness(その時点で発揮可能な体力レベル)」を決定します。
フィットネス=プラスの出力 ・ 疲労=マイナスの出力 ・ preparedness =プラスマイナスの出力の合計。
どのようなトレーニング刺激(=入力)を身体に与えれば、どのような応答・適応(=出力)を引き起こすことができるのか(=外側から見た使い方)については、経験的にもある程度わかっていますし、科学的な研究も進んでいる。
そこで、トレーニングの内容(=入力)を計画し、目的とする適応(=出力)を引き出そうとしている。
フィットネス
- トレーニングによって獲得されるプラスの出力です。一度獲得すると、効果は比較的長く持続します。
フィットネスの「急性の変化量」は小さいと考えられます。別の言い方をすると、1 回のトレーニングという入力に対して、プラスの出力であるフィットネスが増える量は比較的小さいということです。 - その代わり、トレーニングにより獲得したフィットネス向上効果は、時間が経つとすぐに消えてしまうわけではなく、比較的長い期間にわたって持続しやすいという特徴があります。
- つまり、トレーニングによって向上したフィットネスがトレーニング前のレベルに戻るまでに時間がかかるので、フィットネスの「変化の速度」は遅い、ということになります。
疲労
- トレーニングによって蓄積されるマイナスの出力です。短期間で蓄積されますが、回復も比較的速いです。
- 疲労の「急性の変化量」は比較的大きいのです
- その代わり、1 回のトレーニングによって蓄積された疲労はいつまでも残っているわけではなく、時間が経過するにしたがって比較的すばやく減っていくので、疲労の「変化の速度」は速いという特徴があります。
preparedness
- フィットネスと疲労の合計値で、身体的なポテンシャルを示します。
本当は「 preparedness」ではなく「パフォーマンス(競技力)」と直接的に呼びたいところですが、実際のパフォーマンスには他の要因(天候、対戦相手、技術、戦術、心理的要因など)の影響もあるので、あくまでも「身体的なポテンシャル」という意味で「 preparedness」という言葉を使います。
トレーニング直後はフィットネスも疲労もその量(絶対値)が増えていますが、「急性の変化量」はマイナス要因である疲労のほうが相対的に大きいので、結果としてプラスマイナスの合計である preparedness はマイナスとなります。 - トレーニング刺激という「入力」を身体に与えた後 の preparedness という「出力」が時間経過とともに見せる変化の背景には、プラス要因の「フィットネス」とマイナス要因の「疲労」という2 つの存在があり、それぞれが異なる「急性の変化量」と「変化の速度」の特徴を持っていて、その相互関係によって preparedness の動態が決定される、という考え方が「フィットネス−疲労理論」の本質となります。
トレーニング直後はフィットネスも疲労も増えますが、疲労の増加量が相対的に大きいため、preparednessは一時的に低下します。時間が経つと疲労が先に回復していくので、次第にpreparednessが向上していきます。
ディロードウィークの目的と効果
deload week とは「練習やトレーニングにより蓄積した疲労を取り除くために、何週間かに一度、練習やトレーニングを軽めにする週を設けること。または、その週のこと。
目的は、
- ① 疲労が過剰に蓄積してオーバートレーニングに陥るのを防ぐ
- ② Preparedness を高めた状態で翌週からのトレーニングに臨むことができる
疲労の軽減とオーバートレーニングの予防
時間が経過すれば疲労は減っていきますが、疲労が完全に抜けきる前に次のトレーニング(=入力)を実施すると、残っていた疲労に新たな疲労が積み重なるので、疲労が大きくなります。そして、そのような状況が繰り返されると、疲労がどんどん蓄積していきます。
トレーニングの大きな目的は、プラスの出力である「フィットネス」を中長期的に向上させることです。そのためには、トレーニング刺激という「入力」を身体に与える必要があります。
ただし、この入力の大きさや頻度が過剰になって回復とのバランスが崩れてしまうと、「オーバートレーニング」に陥るリスクが高まります。
そのようなリスクを避けるために、
deload week を定期的に設けて疲労を軽減しようとするわけです。
preparedness(体力レベル)の向上
トレーニング後、時間が経つ と preparedness が増えていく」という現象は、 deload week 以外の期間でも起こっています。
しかし、通常レベルのトレーニングをこなしていて「入力」が比較的大きい場合は、トレーニング直後 の preparedness 低下量も大きいため、 preparedness がトレーニング前のレベルに戻るまでに時間がかかります。
多くの場合、 preparedness がトレーニング前のレベルに戻り切る前に次の「入力」のタイミングがやってくるので、 preparedness はどんどん低下していくことになります。
一方、 deload week 期間中は、「入力」の量が減るぶんトレーニング直後 の preparedness 低下量も小さくなるので、トレーニング後の比較的早いタイミング で preparedness がトレーニング前のレベルまで戻り、さらにはトレーニング前のレベルを超えて増えていくと考えられます。
つまり、 deload week を設置することで、その前よりも preparedness を高めた状態で翌週からのトレーニングに臨むことができるようになるわけです。
入力の増加とパフォーマンスの維持
定期的 に deload week を設置し て preparedness の過度な低下を抑えることができれば、ウエイトトレーニングでより重い重量を持ち挙げることができたり、より多くのレップ数をこなすことができたりするので、「入力」を増やすことに繋がります。
「入力」が増えればフィットネス向上効果も高まるはずです。
逆に、 deload week を設置せずにウエイトトレーニングをやり続けた結果、疲労が蓄積し て preparedness が大きく低下してしまうと、挙上重量が下がったり、指定されたレップ数をこなせなくなったりして「入力」の低下に繋がり、期待したようなフィットネス向上効果が得られなくなる恐れがあります。
ようするに「入力」を増やすことでフィットネス向上効果を高めることができる、もしくは「入力」の低下を防ぐことでフィットネス向上効果を維持することができる、ということなのです。
ディロードが必要ない場合
逆に考えると、週を追うごとに疲労が蓄積せず、 preparedness も低下していないような状況においては、 deload week を設置しても意味がないということになります。
むしろ、そのような状況 で deload week を設けて「入力」を減らしてしまうと、フィットネス向上効果が低下してしまうので逆効果です。
ディロードの心理的効果
心理的な効果とは、定期的 に deload week を設置すると、「あと◯週間がんばってトレーニングしたら deload week だ!!」とアスリートが考えることで、 deload week 以外の期間中にトレーニングをよりがんばることに繋がるのではないか、ということです。
ディロードのタイミング
体調の変化に合わせて設定する。
Deload week は「疲労が過剰に蓄積しそうな時」に設置すればいい、という方針に基づいて考えると、
「なんだか最近疲れ気味だな〜」
「疲労のせいか、動きにキレがないな〜」「身体が重い気がするな〜」
と感じ始めたタイミングで、その週もしくは翌週 を deload week にして、練習やトレーニングを軽めにすればいい、ということになります。
主観的な疲労度をモニタリングしながら deload week 設置のタイミングを決めることもできるし、起床時の体重や心拍数等の客観的なデータをモニタリングしながら異常値が出たら deload week を設置する、というやり方でもいいでしょう。
しかしこれでは中長期的な計画を立てづらい。
定期的な計画(proactive)
中長期的なトレーニング計画を立てる段階で、ディロードウィークを予め組み込んでおく方法です。
メゾサイクル(中期間のトレーニング計画)を1つの単位として、例えば3〜4週間ごとに1週間のディロードウィークを設けるのが一般的です。
これだと何かトラブルや、疲労のたまり方に異常があったりするとうまくいかない。
ハイブリット型
お勧めするのは、まずは練習やトレーニングの中長期計画を立てる段階 で deload week 設置のタイミングを決めておき、
もし事前の予想とは異なるタイミングで疲労が過剰に蓄積しそうになったら、必要に応じ て deload week を追加で設置する( = reactive)、というハイブリッド型の運用方法です。
Intro week
Intro week の主な目的 は2 つあります
① 蓄積した疲労を取り除く
② 筋肉痛の程度を抑える
intro week に特有の「筋肉痛の程度を抑える」という目的について見ていきます。
ウエイトトレーニングのプログラムデザインにおいては、メゾサイクル単位でトレーニングの内容に変化をつけることが多いです。
エクササイズが変わるかもしれないし、1 セットあたりのレップ数が変わるかもしれないし、相対的強度(%1RM)が変わるかもしれません。
一般的にトレーニング内容が切り替わるタイミングにおいては、新しい刺激に身体が慣れていないので、筋肉痛が起こりやすいです。
つまり、メゾサイクルの最初の週は、筋肉痛が起こりやすいタイミングなのです。
しかし、 intro week という形で、メゾサイクルの最初の週のトレーニングを軽めにすることで、この筋肉痛の程度を軽減することができます。
アスリートなどは筋肉痛によって感覚が変わりパフォーマンスに影響を与えるため筋肉痛を抑える方がよい。
筋肉痛が発生する確率が高いメゾサイクルの最初の週というタイミング に deload week を持ってくることで、疲労除去と筋肉痛低減の一挙両得を目指すのが intro week
イレギュラーがある場合
トレーニングを休止せざるをえない週があることが事前にわかっているようであれば、その週 が deload week のタイミングに重なるように、その前後の期間のトレーニングを計画するのが賢いやり方
年末年始の直前 に deload week を設置する、なんてことをしてしまうかもしれません。そうすると、 deload weekの1 週間にプラスして、年末年始 の1 週間前後もトレーニングを休止もしくは軽くすることになり、トータル で2 週間近くも「入力」を減らす期間が続くことになります。それだと、フィットネス低下というデメリットが疲労除去というメリットを上回り、 preparedness が大きく低下してしまう恐れがあります。
ディロードの頻度を調節する場合
メゾサイクルを無視し て deload week 設置のタイミングを決めるようだと、効果的にメゾサイクルを計画することが難しくなってしまいます。これは非常に大きなデメリットであり、「 deload week の頻度を増やすときに細かな調整が可能になる」というメリットを遥かに上回ってしまいます
私がお勧めするのは、もう1 つの解決策です。
それは、 deload week の頻度はメゾサイクル を1 つの単位として決めるものの、頻度を増やすときには deload の程度を同時に変更することで、 deload が急激に増えすぎないように調整する、というやり方です。
たとえば、「2 つのメゾサイクルにつき1 回」の頻度 で deload week を設置していたとき は deload week 期間中のトレーニング量 を 50% 程度減らしていたところを、「1 つのメゾサイクルにつき1 回」の頻度に増やした直後は、 deload week 期間中のトレーニング量の減少幅 を 30% 程度に抑えるような形
不要な場合
頻度が少ない
週1 回しかウエイトトレーニングを実施していない場合、トレーニング直後は一時的に疲労が溜まりますが、次のトレーニングまでには十分な時間があるので、その間に疲労は抜ける可能性が高いので、基本的に必要ない。
週1 回という限られた頻度でしかトレーニングができないのであれば、 deload week は一切設けずに、トレーニングができる限られた機会においては十分な負荷をかけてあげて、フィットネス向上効果を高めることを目指したほうがメリットは大きい。
競技動作による疲労
本書では説明をシンプルにするためにウエイトトレーニングに的を絞っ て deload week について解説していますが、現実的にはウエイトトレーニングだけでなく、それ以外のタイプのトレーニングや競技練習まで含めて、総合的な観点が必要になるということです。
疲労蓄積につながっている根本的な原因、すなわち持久力トレーニングや競技練習の内容を軽くするような形での deload が有効でしょう。
疲労が蓄積しない
回復力が高い、強度が高くない場合は疲労が蓄積していかないので必要ない。
ディロードのやりかた
多くの場合は「オーバートレーニングに陥ってしまう疲労の閾値を超えるまでにはまだ余裕があるけど、その閾値に近づかないようにするための予防措置として、定期的に疲労を抜いておく」というイメージ で deload week を設置することになります。
そのような状況においては、やはりトレーニングを完全に休止する必要性は低く、少し軽めにするくらいのほうが好ましいでしょう。
1 週間トレーニングを完全に休止する
しかし、このやり方だと、フィットネスが低下してしまう、というデメリットも大きくなります。まさに諸刃の剣です。 また、1 週間トレーニングを完全に休止すると、トレーニングを再開したときに負荷が重く感じてしまう、もしくは、適切な身体の動かし方(=フォーム)を思い出すのに数セットかかってしまう、等のデメリットが起こりえます。さらには、トレーニング再開時に筋肉痛が起こりやすくなってしまう恐れもあります。
完全に休止するのではなく、少し軽めにするくらいに留めておいたほうが、 deload week の目的には適っているし、メリットが上回る可能性も高いです。
セット数を減らす
「セット数を減らす」というのが、おそらく最も一般的に使われている deload week のやり方です。たとえば、「3 セット ×8 レップ」でトレーニングしているメゾサイクルの最後の週 を deload week に設定して、「2 セット ×8 レップ」みたいにセット数を減らすような形です。
1 週目:3set×8rep@100kg
2 週目:3set×8rep@100kg
3 週目:3set ×8rep@100kg
4 週目:2set ×8rep@100kg←deload week
deload week 期間中に実施するすべてのエクササイズ を1 セットずつ減らすことを考えると、それなりのインパクトがあることが想像できるはずです。
たとえば、1 セッションあたり5 つのエクササイズ× 週3 回でトレーニングをしている場合は、1 週間あたりで考える と5×3= 15 セットを減らすことになるので、それなりの疲労除去効果が期待できます。
一般的にウエイトトレーニングにおいては、強度の高いトレーニングよりも量の多いトレーニングのほうが、疲労が溜まりやすい傾向があります。
これを逆に考えると、トレーニング量(例:セット数)を減らすほうが、トレーニング強度を減らすよりも、 deload week の手法として疲労除去効果が高い、という仮説を立てることもできます。
重要な試合に向けてのコンディション調整方法 の1 つである「テーパリング」に関するメタ分析 によると、
トレーニング強度やトレーニング頻度は維持しつつ、トレーニング量を大幅に減らすことが( 41~60%)、疲労を除去し て preparedness を向上させる効果が高いことが報告されています。
テーパリングについて詳しくは、以下の本を参考にしてください。
どの手法を使っ て deload しようか迷ったときは、とりあえず「セット数を減らす」を選んでおけば、大きな失敗をするリスクは低いでしょう。
deload week を設置するときには、セット数を減らすことをメインの手法として選択しつつ、必要に応じて他の手法を組み合わせることが多いeです。
エクササイズ数を減らす
「エクササイズ数を減らす」というのも deload weekの1 つのやり方です。たとえば、1 セッションあたりのエクササイズ数 を8 個から5 個に減らす、といった感じです。セット数を減らすのとは異なる形でトレーニング量を減らすことができるので、疲労除去効果が期待できます。
たとえば特定の部位に局所的な疲労が蓄積している場合は、それ以外の場所を鍛えるようなエクササイズを削っても、問題となっている部位の疲労を取り除くことはできません。そういう状況では、疲労が溜まっている部位にかかる負荷を減らすことができるように、よく考えたうえで削るエクササイズを選ぶことが重要です。
エクササイズ数を減らす」という deload week の手法を選択するのが適しているのは、同じ身体の部位もしくは同じ動作パターンのエクササイズが複数含まれている場合に限られる。
トレーニング頻度を減らす
ここまで紹介してきた「セット数を減らす」「エクササイズ数を減らす」 の2 つは、「1 セッションあたりのトレーニング量」を減らすよう な deload week のやり方です。結果として、 deload week 期間中の「1 週間あたりのトレーニング量」を減らすことにも繋がります。
「頻度を減らす」例えば、 週3 回ウエイトトレーニングをやっているのを 週2 回に減らすような形です。 Deload week 期間中のトレーニング量が減ることになるので、疲労除去効果が期待できます。
preparedness を向上するためには、トレーニング頻度は減らさずにトレーニング量を減らすのが有効である、とされています。
テーパリング と deload week は、手段として活用するメカニズムは共通しているので、 deload week においても「トレーニング頻度を減らす」という手法の優先順位は高くないと考えていいでしょう。
Deload week においては、まずは「セット数を減らす」「エクササイズ数を減らす」というやり方 で1 セッションあたりのトレーニング量を減らすことを目指し、それでは疲労除去効果が足りないケースにおいてのみ、「トレーニング頻度を減らす」という手法も組み合わせるのが良いかもしれません。
挙上重量を減らす ここまで紹介してきた「セット数を減らす」「エクササイズ数を減らす」「トレーニング頻度を減らす」 の3 つは、大きな枠組みで考えると「トレーニング量を減らす」という deload week の手法です。
強度を減らす
1 週目:3 セット ×8 レップ@ 100kg ・ 2 週目:3 セット ×8 レップ@ 100kg ・ 3 週目:3 セット ×8 レップ@ 100kg ・ 4 週目:3 セット ×8 レップ@ 85kg ← deload week
トレーニング強度」を減らすよりも「トレーニング量」を減らすほうが、疲労を取り除い て preparedness を増やす効果は高いと考えられます。したがって、 deload week の手法の選択肢として、挙上重量(≒トレーニング強度)を減らすことの優先順位は高くありません。
100kgを8 レップ実施しようとすると、疲労の影響でセット終盤にフォームが崩れてしまうような状況においては、挙上重量 を 85kg に減らすようなやり方 も1 つの選択肢にはなるでしょう。
疲労については個人差も大きいので、トレーニング量が多い場合よりもトレーニング強度(≒挙上重量)が高い場合のほうが疲れやすいというアスリートも存在します。そういうタイプのアスリートの場合は、挙上重量を減らしてあげるよう な deload week のやり方を事前に計画してあげてもいいかもしれません。
1セットあたりのレップ数を減らす
「1 セットあたりのレップ数を減らす」というのも deload weekの1 つのやり方です。たとえば、メゾサイクルの最後の週 を deload week に設定して、1 セットあたりのレップ数 を8 から5 に減らすような形です。 ・
1 週目:3 セット ×8 レップ@ 100kg
2 週目:3 セット ×8 レップ@ 100kg
3 週目:3 セット ×8 レップ@ 100kg
4週目:3 セット×5 レップ@100kg← deload week
疲労が溜まってくるとセット終盤でフォームが崩れやすい傾向にあることがわかっているアスリートに対しては、「1 セットあたりのレップ数を減らす」という deload week の手法を事前に選択して計画するのも1 つの手でしょう。
エクササイズを変える
最後に紹介するのが「エクササイズを変える」という deload week の手法です。この手法には、大きく分け て2 つのタイプ(もしくは目的)があります。
動作パターンとしては似ているものの、挙上できる重量が軽くなるようなエクササイズに変更することで、疲労の除去を狙うようなタイプです。たとえば、メゾサイクルの最後の週 を deload week にして、バックスクワットをオーバーヘッドスクワットに変えるような形。
1 週目:バックスクワット3 セット×8レップ@ 100kg
2 週目:バックスクワット 3 セット ×8 レップ@ 100kg
3 週目:バックスクワット 3 セット ×8 レップ@ 100kg
4 週目:オーバーヘッドスクワット 3 セット ×8 レップ@ 50kg ← deload week
オーバーヘッドスックワットというエクササイズの持つそのようなバイオメカニクス的特徴により、挙上重量はバックスクワットよりも軽くせざるをえないので、下半身の筋群にかかる負荷は小さくなります。
結果として deload になり、疲労除去効果 や preparedness が増える効果が期待される。
下半身にとって は deload になるかもしれませんが、バーを頭上に保持するために使われる上半身の筋群にとっては逆に負荷が増えてしまう恐れがある。
それを補うために、ほかの部分で上半身 を deload してあげるような工夫が必要になります。
そこまでセットで考えないと、この deload week のやり方は失敗してしまう。
同じエクササイズを継続して実施することで特定の部位に負荷がかかり続けて金属疲労のような状態になっている場合においては、負荷がかかる場所や向き等が少し変わるだけでも意味があるかもしれません。
パワーリフティングやウエイトリフティングのように、挙上重量を高めることが目的となる競技で、重い重量を多くの量こなしているような場合にのみ、使う機会のあるような選択肢だと個人的には思います。
それ以外のアスリートであれば、他のタイプ の deload week の手法を選択したほうが良い。
どちらのタイプにしろ、「エクササイズを変える」という deload week の手法を選択すると、筋肉痛が発生するリスクがあるので注意が必要です。
そして、筋肉痛が発生するリスクがあるということは、メゾサイクルの最初の週 に deload をする intro week の手法としては、「エクササイズを変える」というのは適していないということになります。
Intro week のメリットである筋肉痛の軽減が難しくなるから。
まとめ
フィットネス疲労理論の
トレーニング刺激という「入力」を身体に与えた後 の preparedness という「出力」が時間経過とともに見せる変化の背景には、プラス要因の「フィットネス」とマイナス要因の「疲労」という2 つの存在があり、それぞれが異なる「急性の変化量」と「変化の速度」の特徴を持っていて、その相互関係によって preparedness の動態が決定される、という考え方が「フィットネス−疲労理論」の本質
というところを理解し、
- 疲労が過剰に蓄積してオーバートレーニングに陥るのを防ぐ
- Preparedness を高めた状態で翌週からのトレーニングに臨むことができる
という目的で、ディロードのタイミング、頻度、やり方をそのときにあったものを選択していくべき。
基本的にはメゾサイクルで計画的に淹れて、セット数を落とすのをベースにやるとよい。

コメント