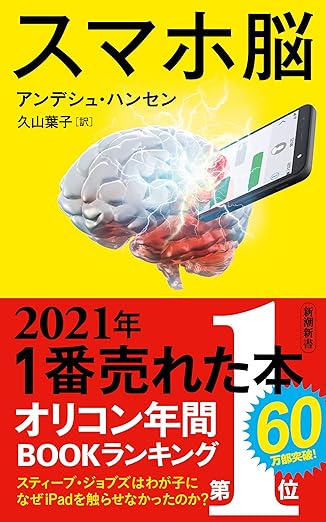
スマホ脳
これは個人的に気になった所や面白かったところ、知的好奇心をくすぐられた場所をまとめた物です。
元々知っている前提や知識も飛ばしてあるので参考程度に見てください。
自分が使いやすかったり、思い出しやすいようにまとめてあるのでほんの実際の流れとは違うこともあります。
抜き出した文章も若干原文を縮めたりしている箇所もあるのであしからず。
前提知識
一旦まとめの前に神経伝達やホルモンの働きなどを知っとくと読みやすいかと思います。
知らなくても解説してくれてたり文脈でほとんど理解できるようにしてくれてますがここでは自分の備忘録もかねてまとめときます。
ドーパミン (Dopamine)
ドーパミンは、快感、意欲、学習、運動に関わる神経伝達物質です。報酬系と呼ばれる脳の回路で重要な役割を担っており、何かを達成した時や好きなものを食べた時などに分泌され、「もっとやりたい!」という気持ちを生み出します。不足すると意欲の低下や運動機能の障害(パーキンソン病など)につながることがあります。
エンドルフィン (Endorphin)
エンドルフィンは、「脳内麻薬」とも呼ばれる神経伝達物質で、鎮痛作用と幸福感をもたらします。激しい運動をした後などに分泌される、いわゆる「ランナーズハイ」は、このエンドルフィンの働きによるものです。痛みやストレスを和らげ、多幸感を感じさせます。
セロトニン (Serotonin)
セロトニンは、精神の安定、幸福感、睡眠、食欲などを司る神経伝達物質です。心のバランスを保つ役割があり、「幸せホルモン」とも呼ばれます。日光を浴びたり、リズム運動をしたりすることで分泌が促進されます。不足すると、気分障害(うつ病など)や不眠の原因となることがあります。
オキシトシン (Oxytocin)
オキシトシンは、「愛情ホルモン」や「絆ホルモン」とも呼ばれるホルモンです。他人への信頼感、共感、愛着を深める働きがあります。ハグをしたり、誰かとスキンシップをとったりすることで分泌されます。子育てや人間関係の構築に重要な役割を果たします。
コルチゾール (Cortisol)
コルチゾールは、ストレスに対処するためのホルモンで、血糖値の上昇、免疫機能の調整、炎症の抑制といった働きがあります。ストレスを感じた時に分泌され、身体を戦闘モードに切り替え、エネルギーを供給します。しかし、慢性的なストレスによって過剰に分泌されると、高血圧や免疫力の低下など、健康に悪影響を及ぼすことがあります。
アドレナリン (Adrenaline) と ノルアドレナリン (Noradrenaline)
アドレナリンとノルアドレナリンは、どちらも闘争・逃走反応に関わるホルモン・神経伝達物質です。
- ノルアドレナリンは、集中力、覚醒、意欲を高めます。危険を察知した時に分泌され、瞬時に身体を反応させる準備をします。
- アドレナリンは、さらに強いストレスや興奮状態の時に分泌され、心拍数や血圧を急激に上昇させ、筋肉への血流を増やして、素早い行動を可能にします。
HPA系 (HPA axis)
ストレスを感じると、脳の視床下部からCRHというホルモンが分泌され、次に下垂体からACTHが分泌され、最後に副腎からコルチゾールが分泌されます。この一連の流れによって、身体がストレスに対処するための準備が整えられます。HPA系の働きが過剰になると、コルチゾールの過剰分泌につながり、様々な体調不良を引き起こす可能性があります。
HPA系は、視床下部(Hypothalamus)、下垂体(Pituitary)、副腎(Adrenal)の3つの器官からなる神経内分泌系で、ストレス応答の中枢です。
内容まとめ
主に引っかかったとこまとめ。
現代人の現状
- 睡眠時間が減り、座っている時間が増え、運動時間は減った。これは長い人間の歴史上、脳からしたら未知の世界。
- 1日に2600回以上スマホを触り、平均して10分に1度スマホを手に取っている。
- スクリーンタイムは大人は3~4時間、10代は4~5時間(2020時点なので現在はもっとスクリーンタイムは伸びている)
- スウェーデン人は9人に1人以上が抗うつ剤を服用
- 抗うつ剤を飲む人が増えているが自殺者は減っている。
- WHOによれば、10人に1人が不安障害を抱えている。
- 10年前に比べて若者の睡眠時間は1時間も減っている。
脳について
- 脳はそもそも体を動かすためにできている。
運動によって集中力を高めとストレスレベルを下げることができる。 - 私たちに様々な行動をとらせ、瞬時に全力で行動に出られるようにするのが感情の役割
- 負の感情が最優先される
- 強いストレスを受けているときは記憶があいまいになることが多い。
- 脳は成人で一日の消費エネルギーの二割を使っている。10代は三割、新生児だと約半分。
- 脳のストレスは本来は三分まで。なぜなら恐怖を感じたとき相手か自分が3分後に死んでいるから。
- 慢性的なストレスは免疫系や精神的な不調の原因になってしまう。
- 強いストレスを受けているとき「闘争逃走」の局面では、「睡眠」「消化」「繁殖行動」すべてを後回しにする。(不眠、消化不良、吐き気、性欲減退などが起こる)
- 睡眠時間が一日6時間以下が10日以上続くと24時間ぶっ続けで起きてたのと同じくらいの集中力にまで低下する。さらに情緒も不安定になる。
- 行動ベースの免疫もあるのではないか?ストレスをうけて免疫系が働く。それが鬱につながるのでは?
- ドーパミンは目の前にあるものに集中するように仕向けて、それが満足と感じさせるのがエンドロフィン。
- 新しい情報を探そうとする本能の裏にある脳内物質がドーパミン。
- 注意残余とよばれる脳が直前までやっていた作業に残っていて切り替わり迄にかかる時間がある。100%の集中力に戻るまでには数分かかる。なのでマルチタスクすると作業効率が下がる。
- ドーパミンは目の前にあるものに集中するように仕向けて、それが満足と感じさせるのがエンドロフィン。食べたいという欲求がドーパミンで美味しいと感じて満足するのがエンドロフィン。
- マルチタスクをするとドーパミンが出て気持ち良くなるためどんどんマルチタスクしようとする。敵に気づく為に気が散るほうが生存に有利だったから。
- 人間はもともと不幸な生き物。進化の過程で満足より不安によって行動することで発展してきた。
- ボスざるはセロトニン量が多い。
これはセロトニン量が多いサルがボスざるになるだけでなく、自分がボスである(社会的地位が高い)ことを理解してセロトニン量が増える。これは人間でも同様。 - ボスざるが命令しても他のサルが見えないようにすると支配力がなくなったと不安になりセロトニン量が減った。そしてボスの地位を失ったサルは行動も変化し、疲れ切ったように呆然としてうつ状態になった。
- セロトニンが減少すると内向的になるが、これはボスの地位から退いたサルが新しいボスの脅威にならないようにするための自然の摂理。
地位の下がった個体は身を引き姿を隠す。体力が回復したら戻ってこられるように。 - ストレスの原則。長期間ストレスを受け続けると気持ちが落ち込む。危険が多いと解釈した世界から逃れるため。自分のいた地位から突き落とされると脳はそこから逃げ出し手地位を奪った相手の脅威にならないようにする。その結果精神状態が悪くなり他人と距離をとることになる。
- うつ病のパターンは2つ、職場や人間関係などの長期のストレスに起因するもの。それから、社会的地位を失ったことに起因するもの。
スマホによる悪影響
- スマホは脳にドーパミンを与えてくれる存在のため、それを奪われるとストレス反応が起きる。
- 夜間のスマホ使用は空腹ホルモンのグレリンの量を増やす。グレリンは食欲増進、体に脂肪をためやすくするホルモン。
- 写真を撮ると記憶されにくくなる(グーグル効果)
- SNSに費やした時間が長ければ長いほど人生の満足度がさがった。
- 投稿しないで見ているだけの消極的ユーザーのほうが積極的に交流するユーザーより精神状態が悪くなる。
- スマホに依存しやすいのは、タイプA(攻撃性高く積極性があり、怒りっぽい、活動的な性格)の傾向があり、自尊心が低いが競争心が強く、自分をストレスにさらしてる人たち。
- 夜間にスマホを使うとドーパミンがでてしまうので入眠のスイッチが入らない。
- 夜間ストレスを受けるとHPA系が働いて入眠が妨げられる。
改善案
- 運動、睡眠、他者との関わりが精神的不調から身を守る3つの重要な要素。
- 体を動かすと、集中力アップ、記憶力向上、不安解消、ストレスにつよくなる。
- 運動時間がわずか五分でも効果ある。
- どのような運動でも認知機能改善に効果あり。
- 適度なストレスにさらされることも必要。※集中が必要なタスク、運動など。仕事で1週間くらい忙しいていどの負荷なら問題ない。
- 週三回45分の、息が切れて汗をかくまでの運動をがよい。
- きついトレーニング(ランニング20分)緩いトレーニング(散歩20分)両方週3で二週間実施。不安レベルはどちらも下がった。特にきついトレーニングの方が顕著に下がった。また、運動直後だけでなく、その後24時間その効果は続いた。
- 運動習慣がある人にはそれほど不安障害がみられない。
- 身体のコンディションがいい人はストレス原因にうまく対処できるので、ストレスシステムを事前に作動させる必要がない。
感想
超ざっくりまとめると、SNS制限してスクリーンタイムを減らしてたくさん寝て、運動するといいよという内容。
運動に関してはどんな種類でもいいみたいだが、一番いい効果が分かっているのはきつめの有酸素運動らしい。
しかし、筋トレを優先しているのでHIITやインターバルを詰めた心拍数も上げるトレーニングなどを積極的にやったりして応用してくか、時間を作って有酸素少しやろうかなと思う。
個人的には最近関心が高いドーパミン、セロトニンなどの神経伝達物質についての興味深い内容などが書かれてたので楽しく読めた。
ボスざるのところと行動での免疫反応の説はあまり聞いた事なかったし、事象と説明を見てかなり腑に落ちて面白かった。
最後のアドバイスの章はすべて実行するのはなかなか難しいができる範囲で試してみようとおもう。
気になった方は是非!

コメント